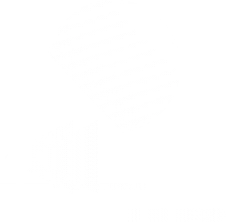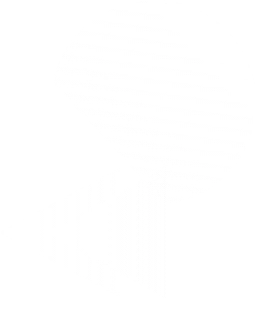ガスレビューコラム
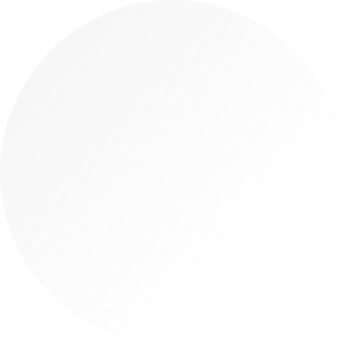
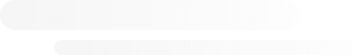
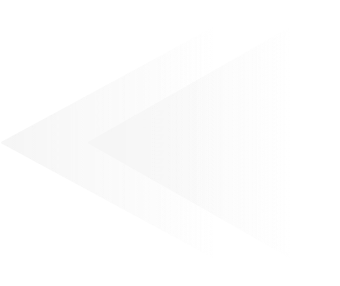
2025.01.31
ドライアイスは本当に悪者なの?
地球温暖化の原因物質として
世界的に削減が求められるCO2(二酸化炭素)。
二酸化炭素の固体での総称であるドライアイスも地球環境の保全から削減していこうという動きが出てきている。
ドライアイスの昇華温度はマイナス78.5℃。冷却能力は同重量で氷の約2倍、同容積の氷の約3.3倍を持っており、宅配便やアイスクリームなどの食品の冷却保存に使われている。
宅配便や食品を冷やしたドライアイスは利用後、昇華して大気中に消えてしまうので、大気中の二酸化炭素の量を増やすことになる。
そこで、こうした冷却用途にドライアイスではなく、繰り返し利用可能な蓄冷剤(保冷剤ともいう)を活用しようというのである。
でも、
本当にドライアイスを止めて蓄冷剤に切り替えれば温室効果ガスの削減ができるのだろうか。
蓄冷剤の利用にもエネルギーを消費する
蓄冷剤は、水と少量の高吸水性ポリマーからできている。
水と高吸水性ポリマーでできたジェルは、氷よりもゆっくり解ける性質を持っており、氷よりも冷たさをキープできる。
蓄冷剤を使うためには先ずは蓄冷剤を電気フリーザで冷やして凍らせなければならない。
ここでは冷却のための電気エネルギーを消費する。
また、繰り返し使用できるということは、使用後は回収し、洗浄して再び冷やさなくてはいけない。
当然、こうした一連のプロセスにもエネルギーを消費する。
一方のドライアイスは、
利用後は昇華して消えてしまうから、回収や再利用の手間がない。
製造から廃棄までトータルで
どちらのエネルギー消費が大きいかで判断する
使う現場だけをみると、
確かにドライアイスは二酸化炭素となって、大気中に放出されてしまうが、
その放出量と蓄冷剤が製造から輸送、再利用に必要なエネルギー消費に伴う排出量とどちらが大きいか、
比較して、どちらが温室効果ガスの排出インパクトが大きいか検証してみる必要がある。
ドライアイスはパワフルな蓄冷剤であり、冷却を要するものの品質管理や安全性の観点から使いやすい蓄冷剤であることは変わらない。
二酸化炭素そのものだから“悪者”と決めつけるのはいささか早計であるといえる。
産業ガスを動画で知る ガスレビューCHANNEL
この問題を動画で詳しく解説しています。
「液化炭酸ガス・ドライアイス 不足の原因と対策」