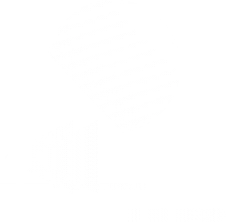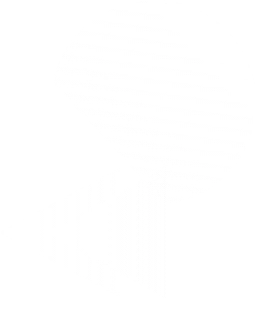産業ガスコラム
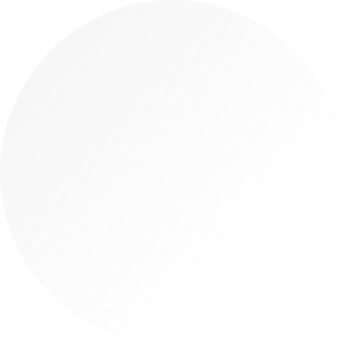
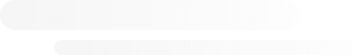
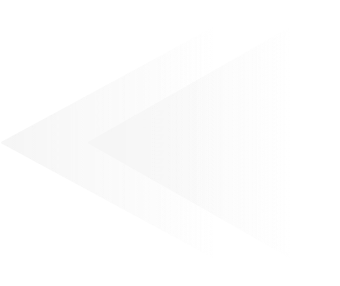
2025.09.09
空気分離 始まりの物語
大気から酸素、窒素、アルゴンなどエアセパレートガスを分離、製造する深冷空気分離技術は、19世紀末に開発され、以来、100年余りに亘って、エアセパレートガス製造の基幹技術として使われ続けている。同技術を利用した酸素発生装置は、異なる技術アプローチで奇しくも同じ1902年にドイツとフランスで開発された。
今回は、深冷空気分離技術の黎明期のお話しである。
製鋼向け、呼吸用に酸素需要増加
時は、19世紀の半ばに遡る。
化学者の努力によってガスの存在や機能は解明されてきたが、いずれも研究室レベルの実験に過ぎなかった。商業用に大規模なガスの生産技術の開発が求められていた。とりわけ、酸素は産業革命以後、製鉄向け酸素富化や呼吸用のニーズが高まっていた。
化学分離が採取の酸素分離
1850年代、フランスの化学者ブサンゴーは、一酸化バリウムが1000℃に過熱されると大気中の酸素を吸着して、二酸化バリウムに変化し、さらに1700℃に昇温すると酸素を離脱し、酸素を回収できることを発見した。これが空気からの酸素分離の最初とされ、実用化の道のりは化学分離法から始まった。
この分離技術の実用化は、ブサンゴーの弟子であった英国人、アーサーブリンとレオン・ケンティン・ブリンの兄弟が引き継ぎ、二人はバリウム酸素プロセスによる酸素発生技術を確立、兄弟は1886年、ブリンズ酸素会社を設立、世界初の酸素会社となる。因みに同社はBOC(現リンデ)の前身企業である。
空気液化のアプローチ
同じような時期に化学分離とは全く異なるアプローチで酸素発生技術が考案されていた。
ガスを液化するという発想である。
既に1800年代初頭には沸点の異なる物質を気液平衡状態にすると分離できることは分かっていた。そこで、空気を液化できれば酸素を分離できるはずと考えられたのである。ボイルシャルルの法則に則り、気体に圧力を加えていくと、容積が小さくなり、最終的に液化するはずであり、アンモニアや塩素の液化には成功していた。ところが、空気や酸素は、いくら圧力を掛けても液化しない。「永久気体だ」と言われたほどだ。
後に圧力だけでなく、温度を下げないと液化しないということが分かり、1877年、フランスの鉱山技師S・カイエテは酸素が約300気圧、-29℃で霧状に液化することを発見した。
酸素液化の道が開かれたのである。
如何に低温を得るか
ただ、問題はどのようにして低温を得るかである。効率良い液化システムでないと、商業ベースでの酸素分離は実現し得ない。19世紀末、フランスとドイツでそれぞれ異なる手法で低温と酸素分離に挑んでいた人物がいた。
フランスの技術者、ジョルジュ・クロードは、気体が圧縮されれば温度が上昇し、膨張すれば温度が下がるという原理を応用、膨張エンジンと呼ばれる仕組みで空気を冷却しようと考えた。1902年、クロードは膨張エンジンによる空気液化に成功した。
一方C・リンデは、ジュールトムソン効果を利用した空気液化に取組んでいた。ジュールトムソン効果とは、気体が、多孔質物質が詰められた管の中を通過する際に膨張し、温度が下がるという現象のこと。ピストンが無くても気体を冷却できる。リンデは1895年に空気の液化に成功。
フランスとドイツ、異なる場所で空気液化に成功した二人は奇しくも同じ1902年にそれぞれ酸素発生装置を開発した。
フランスのクロードはエア・リキード社を、ドイツのリンデはリンデ社を創設、装置開発をガス事業の草創に結び付け、今日に続く産業ガス事業が幕を切っておとされたのである。
日本には開発から5年後に初導入
この二つのプロセスは、酸素の大量生産を可能とし、酸素需要が台頭しつつあった工業先進諸国に瞬く間に広がっていく。日本にはわずか5年後の1907年(明治40年)、エア・リキードグループによって大阪桜島の大阪鉄工所にクロード式20㎥/hの酸素発生装置が設置されたのが最初である。因みにその3年後の1910年には、現日本エア・リキードの前身である日本オキシジェーヌ及アセチレーヌ会社が設立している。
同じ年には日本酸素(現、日本酸素ホールディングス)も設立され、翌1911年にはリンデ方式の流れをくむドイツ・ヒルデラント社製の10㎥/hの酸素発生装置が稼働している。